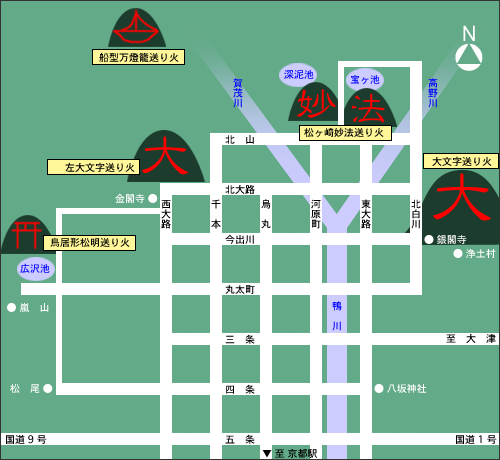8月と云えば日本では「お盆」。 数年前、たまたま表紙のご挨拶を担当したのも丁度8月号で、その
 際には盂蘭盆(うらぼん)のお話をさせていただきました。 今回も、たまたま、
際には盂蘭盆(うらぼん)のお話をさせていただきました。 今回も、たまたま、
西宮在住の親友が贈って下さった本(『私のみつけた京都あるき』 羽田美智子著 集英社)を二ヶ月ほどかけてチビチビ読んでいたのですが、昨日読んだ最終章で、京都五山の送り火保存会の招待で羽田さんが体験された送り火の事が書いてあったので、表紙ご挨拶でお話しすべくインターネットで検索しているうちに、次のような文章が目に付きました。
今では夏の風物詩として有名な大文字の送り火ですが、その起源や由来が謎に包まれている事は意外と知られていません。 長らく日本の首都であった平安京では、そのほとんどの行事や風物は朝廷などによる公式な記録が残っていますが、大文字の送り火については、そのような公式記録がなく、「いつ、だれが、何のために」始めたのかは、謎のままになっています。 「あくまでも民衆による自発的な行為だったので記録されなかったのでは」とも言われていますが、今でも現代人の目を惹く大文字、昔の人々にとっては、さぞかし夏の夜の一大パノラマだったでしょう。 その大文字に朝廷が何の意見も述べていないのは不思議ですし、また昔は京都周辺のほとんどの山々で送り火が燃やされていた時期もあるとも伝えられており、そのような事が朝廷の許可なく行われていたとは考え難いです。 それとも、山々に灯す送り火は、わざわざ書き留める必要もないほどの自然な行いだったのでしょうか。 その謎を解きあかすには、「日本人とお盆」、「京都でのお盆」を探ってみなければなりません。 http://kyoto.nan.co.jp/knowledge/daimonji.html
プランタムラ伸子さんから投稿いただいた今月号特集「ルーツを探る」(3ページ)も、日本人と
お盆・京都でのお盆の背景を探るのと同じように、ご先祖様達を通して Who We Really Are を知ろうとする我々の本能的な願いが篭っているように感じ、心温まるうちに読ませて
いただきました。 (伸子さん、ありがとうございます!)
伸子さんと同じく伊系米国人の家系に嫁いだ私にも、日本とアメリカ(&イタリア)を母国とするご先祖様達が大勢いらっしゃいます。 今年の夏、お里帰りでお盆の辺りは京都滞在の予定
だったのがキャンセルされて、京都の五山送り火の行事は体験できませんが、お盆を好機に、気分を新たにして、今日の自分達の存在を可能にしてくれたご先祖様達を心に、灼熱のタンパの青い空に向かって、感謝のお祈りを捧げます。
フィカラかこ 記
注釈: 下は京都五山送り火の地図です。(上記サイトから拝借)